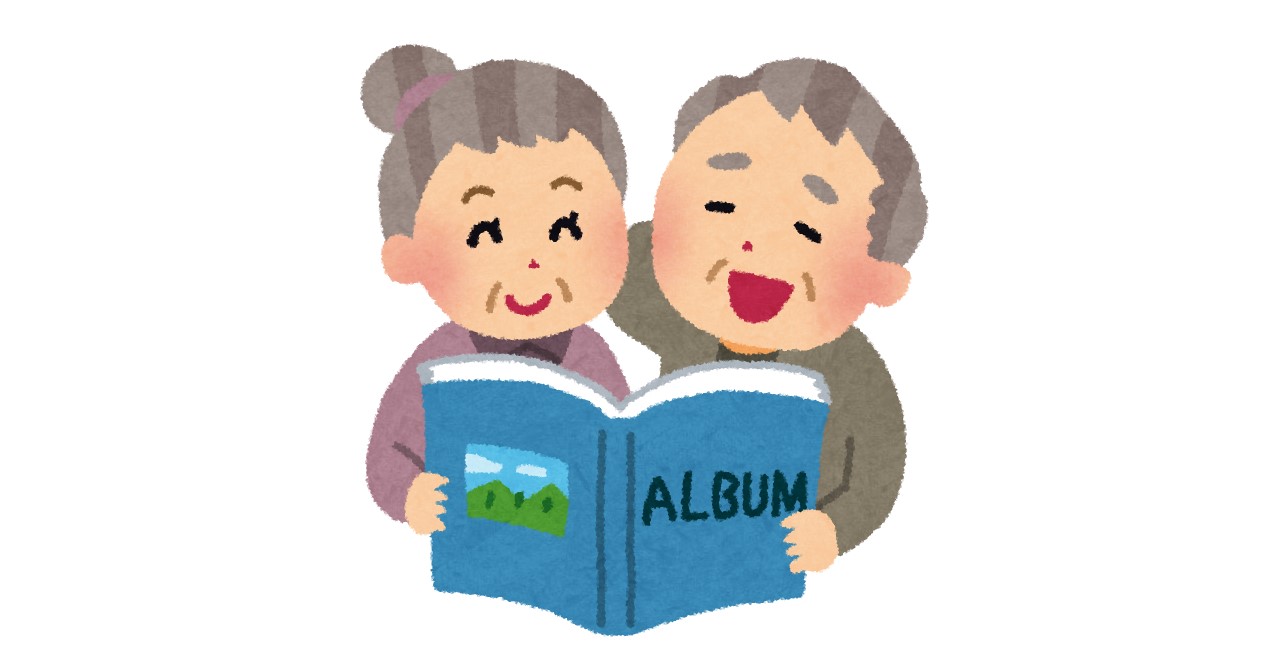顧客とは人の一種である。
世の中のあらゆる顧客という人から偶有性をすべて捨てると、「商品価値を受け取る」という属性だけが残る。
ゆえに、顧客という人の本質とは「商品価値を受け取る」という属性である(「本質とは何か」参照)。
よって、顧客とは「商品価値を受け取る人」である。
商品価値とは「対価と交換される価値」であるから、顧客とは「対価と交換される価値を受け取る人」でもいいし、単に「対価を支払う人」でもいい。
もちろん、顧客が受け取る商品価値は、顧客の頭の中に生まれるものだ。
では、顧客とは誰なのか。
消費者向けビジネス、すなわち「B(Business) to C(Consumer)」ビジネスを行う企業にとっての顧客は、消費者である。
このことに疑問を差し挟む余地はないだろう。
他方、企業向けビジネス、すなわち「B(Business) to B(Business)」ビジネスを行う企業にとっての顧客は、誰なのか。
世の中がそうするように「顧客は商品を買う」ことを前提とすれば、B to B企業にとっての顧客は、自社の商品を買う、目の前の取引先企業である。
しかし、本質的に「顧客は商品ではなく商品価値を買う」。このことを前提とすると、答えは違うものになる。
あらゆる企業が提供する、あらゆる商品価値を買う=あらゆる商品価値の対価を支払う者は、元をたどれば消費者だ。
ならば、B to B企業が提供する商品価値の対価を支払う者は、目の前の取引先企業ではなく、その向こうにいる消費者であることになる。
B to B企業は、消費者が支払う対価を目の前の取引先企業を経由して受け取っているだけなのだ。
よって、B to B企業にとっての真の顧客は、目の前の取引先企業ではなく、その向こうにいる消費者である。
そして、消費者の集まりは、社会である。
だから、あらゆる企業にとって、顧客は消費者であり、消費者の集まりである社会である。
このことは、経済学の教えるところでもあるが、そこから経済学が教えないことも見えてくる。
消費とは、「①使ってなくすこと ②経済で、人間の欲望を満たすために財貨を消耗する行為」(精選版 日本国語大辞典)である。
要は、消費とは「使ってなくしたり、消耗したりすること」だ。
ならば、消費者は、商品価値を使ってなくしたり、消耗したりする人であることになる。
しかし、実際には、消費者は、商品価値を使ってなくしたり、消耗したりしない。顧客の頭の中で認識が生む作用である商品価値は、使ってなくしたり、消耗したりするものではない(「商品価値とは何か」参照)。
また、商品についての記憶がある限り、消費者は、それを再現することで商品価値を享受し続ける。青春時代の記憶の場合は、時が経つほど美化されて商品価値が増えることさえある。
つまり、顧客である消費者は、商品価値を消費しない。
本来、消費者は「(商品価値の)享受者」とでも呼ばれるべきものなのだ。
経済学者や経営学者が「消費者」という呼称に異議を唱えず、そのまま使っているのは、残念なことである。